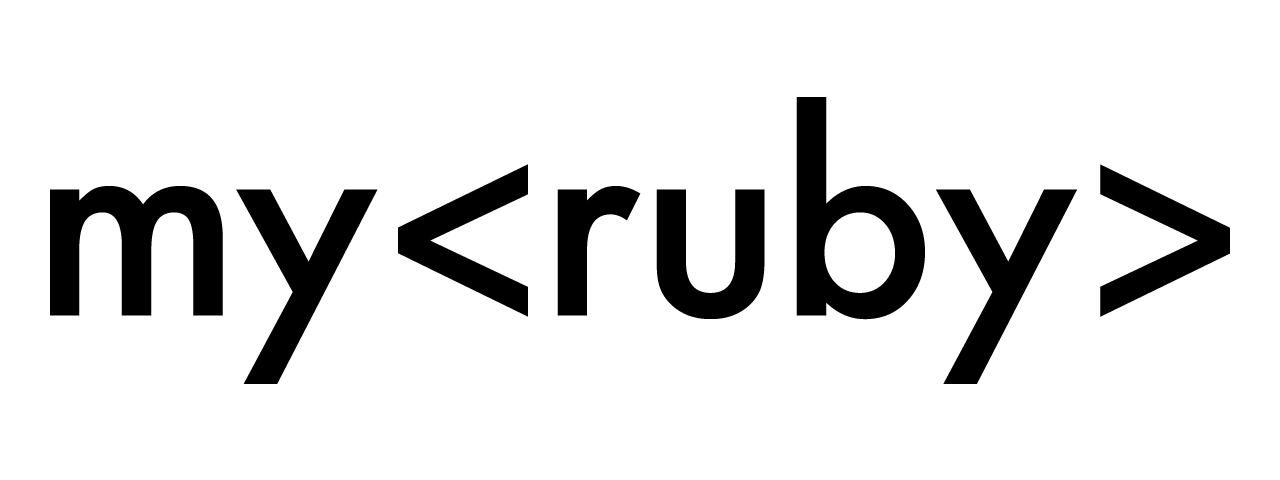風蕭々として、枯槁の木々が寂寥の空に影を落とす。日輪は既に西の山に没し、残照が万象を茜色に染めていた。この辺鄙な山里には、古くから伝わる秘話がある。
里の者は、この山に棲まうとされた奇偉な生物を畏怖し、その存在を口にするのを忌んでいた。曰く、その獣は鵺に似て、虎のような牙と、蛇のような鱗、そして鷲の如き翼を持つという。その咆哮は山嶺を揺るがし、夜闇に紛れて里の家畜を攫っては、瞬く間に天へと消え失せるのだと。
里の長は、その獣の被害が愈々甚だしくなった折、村の若者たちを集めた。彼らは皆、この悲劇の連鎖に終止符を打つべく、勇んで山へと入ることを決意した。しかし、彼らが山中で出会ったのは、鵺ではなかった。それは、狒々のような巨躯を持つ老猿だった。
老猿は、彼らに敵意を見せることなく、ただ静かに蟠踞していた。その眼は深奥を覗き込むかのように澄んでおり、彼らの胸中を見透かしているかのようだった。若者たちは、その圧倒的な存在感に気圧され、一歩も前に進めなかった。
その時、一人の若者が、老猿の足元に咲く、見るも清純な梔子の花を見つけた。彼は、その花が何故か老猿のいる場所でしか咲かないことを知っていた。その花に秘められた力、それは、この山を穢す悪意を払い、清らかな魂を育む力だと、里の古老が語っていた。
若者は意を決し、懐から取り出した玉串を、震える手で老猿に差し出した。玉串は、清らかな水で清められ、里の守り神に捧げられる神聖なものだった。老猿は、その玉串を無言で受け取り、ゆっくりとそれを噛み砕いた。すると、その巨体が光を放ち、徐々に縮小していった。
光が消えた後、そこにいたのは、年老いた一人の修験者だった。彼の顔には深い皺が刻まれ、その眼差しには、長きにわたる孤独と、世俗との隔絶が滲んでいた。彼は、かつてこの山で修行に励んでいたが、修行の過程で異形の姿に変容してしまったのだという。彼が家畜を攫っていたのは、里の者に己の存在を知らせるためであり、決して悪意からではなかったのだと。
若者たちは、彼の悲しい顋に手を添え、彼の孤独を慮った。彼らは、修験者を里に連れ帰ることにした。里の者は、初めは怪訝な顔をしたが、若者たちが語る真相に、やがて涙を流し、修験者を温かく迎え入れた。
それからというもの、この山では家畜が攫われることはなくなった。そして、里の者たちは、その修験者のことを山神と呼び、深く尊崇した。彼が里で穏やかに過ごす姿は、里の者たちに、外見にとらわれず、本質を見抜くことの大切さを教えてくれたのである。